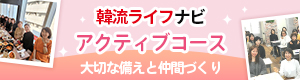取材レポ・コラム
『復活』『魔王』のパク・チャンホン監督、キム・ジウ脚本家インタビュー
2007年10月「韓流ナウ」(web)

田代: まず、お二人すごく名コンビだと思うんですけど、いつごろからどういう縁で一緒に作業をするようになったんですか。
キム作家:12~13年ぐらい前でしょうか、KBSで『新世代報告 大人たちは知らない』という、高校生を扱ったドラマがありました。(注:日本でいう『中学生日記』のような感じのドラマだそう)私はそのときはデビューしたばかりの新人作家だったのですが、機会があるたびに「できたらパク監督とやりたいなぁ」ということを言っていたら、たまたまちょっと縁があって、「じゃあ台本を持ってきなさい」ということになりました。毎回、毎回、作家と監督が違う人と組んでやるというのがそのドラマシリーズで、あるときご一緒できたのですが、一緒にやることになってほんとにびっくりしたのは、私が書いた台本についての解釈がすごく素晴らしくて感動したんです。それで、やっているうちにほんとは監督と組むはずだった作家さんが何か書けなかったりとか、ちょっと用事があってできなかったっていうときに、たまたま私が3回ぐらい、やっぱりまた監督と組むことになって、やればやるほど、やっぱり自分の世界をよく理解してくれる方だなと思って、今まで続くようになりました。最初は今と違ってちょっときつい感じですね。お話もあまりする方じゃなかったんで、ちょっと怖いなというイメージはあったんですけれど。
田代: それ以降、ずっと一緒にやっていらっしゃいますけど、それはキム作家の方から「ぜひ監督と」ということなのか、監督の方から「ぜひやろう」ということなんですか?
パク監督:私が一緒にやろうと言ってます。
田代: パク監督はキムさんの台本を読んで、今までどういうふうに感じていらっしゃるんですか。
パク監督:最高ですよ。彼女の書く台本は、ほんとに人間に対する探求というか理解があって、人のいいところを探り出して書くということは、すごく難しいことだと思うんですけれど、彼女はそれをすごくうまいんです。シナリオを書くということはすごく難しくて、ほんとに言葉で表現できないくらい難しいものだと思うんですけれども。彼女の描く人間っていうのはすごく魅力的で、最初読んだときほんと鳥肌が立つぐらいとても感動したことを覚えています。
田代: それはその最初の新人のときの台本からですか。
パク監督:ほんとに最初の、ほんとの初作品を一緒にやりました。実はその最初の作品っていうのがすごく難しい素材だったんですね。母親の過保護を受けた子どもの話で、どちらかというと心理劇のようなものだったんですけれど。それを書くのに、彼女はほんとに自分の足でいろいろ資料を集め、調査して歩いて、ほんとに素晴らしいものを最初に書いてきたことを今でも覚えています。人間なので年相応なものを書くだろうと思うんですけど、彼女を見ると、「この人100年ぐらい生きてるんじゃないか」と思いますよ。
キム作家:監督はいつもこんなふうに、私のことをとってもほんとに褒めてくださるんですけれど。監督は人をおだてて乗せるのがうまいんです。もし私がシナリオを書いたとすると、まずいいところをほんとによく褒めてくださって。あと、補充する点はちょっと補充してくださった後に、その問題点とかちょっと不足点を正確に指摘されます。つまり、人の扱いがとてもうまい監督さんだと思います。
田代: いいパートナーを見つけ出すのってとても難しいと思うんですけど。お互いほかの人ともやったことがあると思いますけど、やっぱりその中でも一番よき理解者だなと感じられますか。
キム作家:ほんとそうですね。ほかの人には感じられなかったものを、お互いが感じ取ったというか。
パク監督:彼女の生きざまがすごく好きなんです。なので、彼女と一緒に何かをやったら多分幸せになれるだろうというような。それがとにかく、彼女と一緒にやる原動力のようなものになってると思います。
田代: 生きざまというのは、例えば?
パク監督:かっこいいんです。彼女は弱いものですとか、貧しい人たちのような、何も持たない人に対する配慮というか、そういったものができるんです。なので、それがただ台本にだけそれが表れるのではなくて、彼女自身がほんとに普段からそういう行動が取れるということに対して僕は感動し、ほんとに尊敬もしてるんです。なので、台本以外に彼女の生き方に対する信頼というものは、確固たるものがあります。
田代: 逆にキム作家から「監督のここがよくて私はいつも監督とやるんです」というところは。
キム作家:なんだかお互い褒め合うのもなんなんですけど(笑)。今、私を褒めてくださったのは、そのまま監督も同じだと思うんですね。例えばの話なんですけど、ミニシリーズでやはり『学校』というものをやっていたんですけれど、普段はあまり現場に行かないんですけれど、そのときたまたま現場に行ったとき、やはり学校なので主人公は何人かがいるわけですが、画面に顔さえ写らないような子たちも何人もいるわけです。でも監督はそのエキストラっぽい子たちの名前も一人一人覚えて、きちんとその子たちのフォローをするということを忘れないんです。 なので、ほんとにミニシリーズ『学校』が終わったときは、すべての学生が監督のことを囲んで胴上げみたいなものもしたりして、ほんとに人気があるんです。そういう監督を知っている私たちは、監督のことをほんとに冗談っぽくなんですけど「パクカリスマ」というふうに呼ぶんです。そのカリスマというのはいろんな意味があると思うんですけれど、人々が集いたい、監督の横にいつもいたい、スタッフもそうですし俳優もそうですし、彼の横にいてそばにいて仕事を一緒にしたいという意味でのカリスマなんです。
また、監督はとっても頭がよくって。俳優さんに対しても私に対してもそうなんですけれど、短い時間でものごとをきちんと処理されるんです。長い間時間をかけて何かぶつぶつ言うんではなくって、「これ、これ、これ」というような短時間でほんとに分かりやすくいろんなものを指摘して、そしていい面を引き出そうとしてくれるので、私としてはとてもやりやすいです。
田代:本当にいいパートナーシップなんですね。
キム作家:ほんとこれも冗談なんですけど、私の周りの作家たちは、「いつになったら監督を放してくれるの。私たちに機会が来ないじゃないか」と。「早く別れてくれ」と言われるんですけれども、私は私で「監督が嫌というまでやるわよ」といつもその友達には言ってます。その彼女たちはちょっと絶望してますね、今の状況に対して(笑)。
田代: でも、しばらくずっと二人でやってるんですね。これは何年ぐらい。
パク監督:僕はこの12年、彼女としか組んでません。ただ、キム作家は、僕の助手が監督デビューするときに、1時間ドラマを何本か書いてあげてますね。
田代: ほかの人とやってみたいとかお互い思ったりしませんか。
キム作家:周りは、ほんとこの二人をどうにかちょっと離そう、離そうと思うんですけど。
パク監督:実は別の監督たちもキム作家とやりたがっていて、列をなして並んでるんですけど、僕が「駄目、駄目。もう僕が彼女とやるんだから」といって、皆さんを蹴散らしてるんです(笑)。
田代: 今回、『魔王』はどちら側から出た企画だったんですか。作品によってどちらからというのはあるんですか、いつも。
パク監督:だいたいほとんど彼女が書きます。
キム作家:いえいえ、ほとんど私がやってるというのはうそで。企画というのはもともとそんなにぱっと出るわけではなくて、いろんな話をするうちに一つ一つ積み重ねてはじめて、そのテーマだったり人物像だったり、いろんな絵が出てくると思うんです。ほんとに一つ終わると、また次のドラマについて二人でいろいろ話し合って、そして、こういうふうにしようか、ああいうふうにしようかって、そんな話から始まって大体出るわけですね。それを書くのが私です。
田代: じゃあキャスティングについては?これだけ長いコンビですと、お互いの中でアイデアを出し合うんじゃないかと思いますけど。
キム作家:それは全面的に監督がやります。監督が決めてそこに私を呼ぶんです。この人でやるからというふうに。全部決めて、最後に私に聞くだけ。私は「この人でやるから」と言われると、「でもちょっとこういう面が心配です」と言うと、彼はそれに対してすぐにその場で「大丈夫。僕がこうやってこうするから」って言って必ずそれを実行されるんで、私に許可を得るなんていうそういう次元じゃありません。事後報告です。
田代: 今回の『魔王』でオム・テウンさんを再び起用したっていうのは、『復活』との関連性をあえて持たせたかったんですか。
パク監督:いわゆる同じ復讐劇でまた次の作品、すぐ次の作品ですよね。その作品に彼をもう一度主役で登場させるということは、ある意味無理というか、ほんとに同じスタッフで、同じ作家で、同じ監督でやるということはある意味イメージが重なって、もしかしたらほんとに周囲の言うとおり無理だったかもしれないんですけど、あえてそれに挑戦したというふうな感じでしょうか。
また、それをやってのける自信も私たちにはありましたし、あと、彼の演技力を全面的に信じていたものですから。
あともう一つは、『復活』では復讐する側、そして『魔王』ではされる側というような、そういったちょっとした差別化を見せること。それと、もう一つ大きなところは、やはりキム作家が書くときにオスはオム・テウンでイメージして書いてたということです。
田代: そうだったんですか。
キム作家:『魔王』のシノプシスを読むと、男優だったら、どちらかというとスンハのほうに魅力を感じて絶対やりたいと思ってしまうと思います。彼のキャラクターはすごく強いですし、あと、やっぱりかっこよく出ているんですね。ただ私は、やはりオスに対して繊細な演技力を要求しましたし、また『復活』とは違う、オム・テウンさんが演じる繊細さをちょっと見せたいというのもあったんです。オス役としてまた違った魅力を見せたかったんです。
田代: 監督はその日に一番いい演技をした人に賞金1,000ウォンをいつもあげていると聞いたんですけど。それはいつごろからどういうきっかけでやるようになって、『魔王』では結局誰が一番もらったんですか。
パク監督:1万ウォン、5,000ウォン、1,000ウォンです。
6年くらい前の『あの青い草原の上で』からですね。あのときから始めて……。そのときは撮影監督が一番だったかな……。
別名「パク・チャンホン奨学金」というように呼ばれています。俳優がもらう場合は、学用品も買ったり、本も買って「もっと勉強しろよ」という意味もありますし。あと、スタッフがもらったときは、「もっと頑張ってね」という励ましの意味を込めてやっています。
もう僕の助監督が僕がそれをやると知っているので、ピン札をいつも準備しているんです。
田代: 俳優ではチュ・ジフンさんがたくさんもらったと聞きましたが。
パク監督:そうですね。一番多くだったかはわからないけど、ジフンにもあげましたよ。
田代:本日はいろいろなお話をありがとうございました。