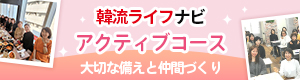取材レポ・コラム
ボーダーレスなドラマ作りと俳優たち
オリコングループ発行「月刊デ・ビュー」2005年5月号より(※掲載元の許可を得て載せています)
最近の韓国のドラマはアジア各国で巻き起こっている韓流ブームを受けて、海外を意識して制作されている。海外をロケ地にしたり、または外国の俳優を出演させたり、方法は様々だが、徐々にボーダーレスの面白い試みとなっている。
そんな中で、今BS日テレで放送中の『ガラスの華』はドラマの一部が、日本の神戸を舞台にしている。幼いころ川でおぼれたのを拾われて日本につれてこられて成長した男性という設定で、韓国俳優のイ・ドンゴンが日本名を名乗って日本人として生きている韓国人として登場する。当然日本語をしゃべる場面も出てくるのだが、残念ながら、日本で育ったという設定にしては、聞いていてちょっとつらい日本語だった。
ちょっと前の映画になるが、『ロストメモリーズ』でのチャン・ドンゴンも、日本の占領下にある都市で生まれ育った設定のために日本語をしゃべっていたが、これも努力の跡は見えるのだが、流暢とは言いがたかった。
よく韓国俳優が来日して日本の記者たちから聞かれることは、「日本の作品に出演してみたいですか?」ということだが、そういう時はほぼ必ず、「機会があれば挑戦してみたいですが、言葉の問題があるので、まずは日本語を勉強してからです」との答えが返ってくる。
確かに、言葉は大事で、日本語がちゃんとしゃべれてしかるべき設定にもかかわらず日本語が下手だと、その役の説得力が欠けるのは確かだ。だが、台湾や中国のやり方を見てみると、俳優自身がそこまで自分でセリフをしゃべることにこだわらなければ、もっと可能性が広がるのではと思えてくる。
台湾や中国は早くから自国のドラマに人気の韓国俳優を抜擢してきていた。それも韓国人としてというわけではなく、もう中国人としての扱いだ。幸い、顔立ちが同じ東洋人ということで違和感がないので、言葉の問題は吹き替えでOKということになっているのだ。
現在BS日テレで放送中の『エーゲ海の恋』はこのいい例だ。『イヴのすべて』などで日本でもおなじみの女優チェリムを迎え、台湾スターのアレック・スーとピーター・ホーが三角関係を繰り広げるのだが、3人とも上海に住む中国人の設定で、出会う場所が旅先のギリシャという豪華さ。台湾も韓国もどこにも出てこず、まるでどこの国のドラマか、パッと見ただけでは国籍不明だ。
このドラマでの主演の一人ピーター・ホーは、日本映画の『T.R.Y』や『着信あり2』、『仮面ライダー555』などにも出演経験があり、言ってみればボーダーレスの経験は豊富な俳優だ。そこで、『エーゲ海の恋』で、チェリムと共演したことについて聞いたところ、「感じたのは、言葉は別に問題じゃないということです。人間と人間との付き合いは言葉だけじゃないでしょ。チェリムさんとも最初は通訳さんを通してましたけど、彼女がセリフを言っているとき、彼女の目を見ればでだいたい何を言ってるかわかるようになるんです。どんどん通訳が必要なくなって、自分で感じるようになる。例えば二人が、撮影じゃなくてもボーっと一緒に座って、たまにポツリと言っても気持ちがわかるようになりました」と語っていた。もっともピーター・ホーは育った環境からして国籍の異なる人たちとの作業には慣れているのだとか。
「台湾ではアメリカンスクールで西洋教育を受けてきましたし、13歳から21歳までずっとカナダのトロントで育ったんです。カナダは世界中で一番いろんな国の人がいる人種のるつぼで、いろんな国にいろんな性格の人がいて、国籍の違いというよりも、性格の違いという感じだと思っています」という。今後更に来たるべくボーダーレスの時代に立ち向かっていくには、この精神にヒントがあると思う。
延長戦コラム
海外ロケの作品が増えている韓国ドラマ。去年から今年にかけての話題作は軒並みそうだった。『バリでの出来事』『パリの恋人』『ラブストーリー・イン・ハーバード』と、タイトルにずばりロケ地が入っているものを始め、オーストラリアに養子に出された男性の孤独な人生と愛を描いた『ごめん、愛してる』、日本が出てくる『ガラスの華』、そして1月から3月まで放送され、ニューヨークロケをした『悲しき恋歌』などだ。韓流ブームを巻き起こしているのがドラマだという自負からか、各国から高値でオファーされるからか、予算を掛けて、だんだんと大作化していっているようだ。
ドラマ本編だけでなく、宣伝にも力の入れようがうかがえる。『悲しき恋歌』では、ドラマの内容を凝縮したような30分にも及ぶミュージックビデオ(以下MV)をわざわざ1億円近くをかけて制作した。このMVのときはまだソン・スンホンが出演しており、その後兵役問題で軍隊に行ってしまったから、今となっては幻の貴重なMVになったのが皮肉だが、こうした思い切ったプロモーション方法を仕掛けられるのも、活気のある証拠だろう。