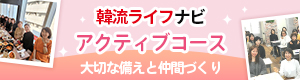取材レポ・コラム
映画&ドラマで見るドラマチック韓国
⑫いまだに続く海外入養児
東洋経済新報社「韓国はドラマチック」(2003年7月発行)より。記事の転載禁止
韓国のドラマを見ていると、やたらと孤児が出てくる。
中でも韓国で特徴的なのは、
海外に養子にやるという海外入養児の存在だ。
この海外入養児の存在が最初にクローズアップされたのは、
1989年11月に2回にわたりMBCテレビの
「人間時代」で紹介されたドキュメンタリーがきっかけだった。
その後、この話は1991年に、
『スーザン・ブリンクのアリラン』として映画化された。
スウェーデンに養子に行かされるという特異な運命を通して
自我を発見していくひとりの女性の成長の過程を描き、
彼女が韓国に帰ってきて実の親を探すというストーリーだった。
主人公のスーザン・ブリンクは、1963年に
一男四女の末っ子として生まれたが、父親を早くに亡くし、
母親は貧しい暮らしの中で、1966年に
末っ子の彼女を養子に出すことを決意する。
そしてスウェーデンの養父母に引き取られるのだ。
彼女は 養母からいじめを受けるのから始まって、
その後も過酷な人生を送るが、1989年、偶然に
韓国のテレビ局で企画した海外入養児特集番組に出演したのがきっかけで、
実の親を探すようになるのだった。
このスーザン・ブリンクをチェ・ジンシルが演じて話題になった。
この作品の印象が強いのか、その後も韓国のドラマや映画で海外入養児が
出てくる場合、たいていは韓国に強い思慕を持っているか、
また逆にひどく避けているかで、幸薄いかわいそうな存在として描かれている。
『ラブ』は、サンフランシスコに養子にやられた
海外入養児の女性ジェニー(コ・ソヨン)と
挫折気味のマラソン選手ミョンス(チョン・ウソン)のラブストーリーだった。
このジェニーという女性は、幼いときに養子としてアメリカに来たが、
養父母が離婚したのをきっかけに行く当てがなくなり、
海外入養児たちの世話係が経営しているというクリーニング店に
ぶらりとやってきて、そのまま住み着いていた。
ジェニーは、望郷の念が強く、料理も韓国風にこだわるし、
韓国の国花のむくげの花を、知り合いから分けてもらった
韓国の土で育てている。
そんなジェニーが仕事の合間に韓国の仲介業者に電話で、
一生懸命自分の特徴を伝えて母を捜してもらっている。
「4歳で平和孤児院に入って背中の左にほくろがあって
右膝に傷跡があって、足の人差し指と中指が同じ長さなんです。
普通の人は中指が長いけど、私は同じなの」
でもようやく見つかった母親は、再婚して子供を3人もうけ、
今の夫はジェニーの存在を知らないと言う事実を知らされる。
さびしそうに言うジェニー。
「会えないけどごめんねっていったのよ。
アメリカにいるからよかった、幸せにってさ」
一方、生まれ故郷を避けようとしていたのが、
『ホテリアー』のシン・ドンヒョク(ペ・ヨンジュン)だった。
ドンヒョクは、ホテルのM&Aの専門家で、
親に捨てられ海外に養子に出されたことが心の傷になっていた。
韓国から仕事を依頼されても「韓国だろ、興味ない」と
あえて断ろうとさえしていた。
それが結局は、一目ぼれした女性のために
韓国に21年ぶりに戻ることになる。
とにかくドンヒョクは、その生い立ちからか、
隙のない、仕事一筋のクールな人間になっている。
しかしそうはいっても実父への思いは薄れず、探し出して訪ねていく。
生活保護を受けながら、なじみの店でご飯を食べさせてもらっている
みすぼらしい父親を前にして、他人を装いながら
父親と世間話をする場面だ。
ドンヒョク「お子さんがいらっしゃるんですか?」
父「女房が死んでから子供を留学に出したんだ」
店のおばさん「留学だって? 養子に行かせたのも留学と言う?
バクチにはまって子供なんか後回しだったから、
アメリカに孤児を連れていく話を聞いて喜んで行かせたのよ」
父「だってアメリカへ行けば飢え死にはしないと聞いたし、
いい服着て肉が食べられて勉強ができればいいだろ」
ドンヒョク「子供たちを行かせた後、会いたいと思ったことは?」
父「会ってもな、もう自分の子供じゃないし」
ドンヒョク「でも実の子供です。父として
捨てた子供に悪いと思う気持ちや罪悪感は?」
父「考えても仕方ない。俺もあいつらもそういう運命なだけだ」
ドンヒョク「親子の関係が忘れようとして忘れられる関係ですか?
断ち切ることもできず、一生自分の親を恨んで生きることが
どんなことかわかりますか。自分が捨てられたということで
誰にも心を開けず、狂ったように勉強して仕事して成功しても、
ただのひと時も幸せを感じたことがなかったとしたら」
父「……!?」
ドンヒョク「あなたがどう生きているのか一度は見ておきたかった。
それだけです。二度と会うことはないでしょう」
そして息子だと気づいた父親が後を追うのを振り切って立ち去るのだった。
実は彼には妹がいるが、その妹も
アメリカの別のところに養子に出されていた。
妹は生活が荒れていて、悪い仲間に引きずり込まれそうなところを
救われて韓国に戻ってくるが、このふたりとも
互いを兄妹とは知らずに顔を合わせ、
中盤になってその事実がわかるという設定になっていた。
この妹のほうは、父親が生きていることを素直に喜び、
会えて嬉し涙を流していた。
韓国での海外入養は、朝鮮戦争後の1955年、混血孤児8人を
養子にしたアメリカのホールト児童福祉会がその始まりだった。
現在はアメリカ、ヨーロッパ地域を中心に約20万人程度が
海外で暮らしているそうだ。
韓国ではこの海外に養子をやることを孤児の海外輸出という言い方をする。
というのも、 養子システムが、
社会福祉という次元だけでされてきたものではなく、
1970年代末の段階では、養父母になりたい人が
養子を受け入れるときの費用として、
子供ひとり当たり200万ウォン(約20万円)を支払い、
養子の国、韓国を補助するために使われることになっていたという。
つまり、子供を売ってお金を得ていたことにもなっており、
こうしたことから韓国ではこうした事実を恥ずかしいことと
とらえているようだ。しかし海外入養を恥ずかしいと考えることじたいが
入養児に対する偏見にもつながり、そういう意識では
国内入養も増えていかないと言う意見も出ている。
そもそも韓国は、血縁意識が非常に強い国民だ。
そのため孤児を養子にすることに対しての偏見が根強く、
うまく養子になれても、その子も、またその家自体も好奇の目にさらされ、
つらい目にあいがちなのだという。
それよりは、養子に対して偏見の少ない海外に行かせたほうが、
その子にとっても幸せだという考え方がある。
そのため、韓国では海外入養40周年の1995年に、
海外入養制度をなくそうとしたが、
結局は存続することになったという社会事情があるのだ。
参照作品
『スーザン・ブリンクのアリラン』
1991年作品
監督=チャン・ギルス 脚本=チャン・ギルス、ユ・ウジェ 出演=チェ・ジンシル
貧困のためスウェーデンに養子に出された少女ユスクが、引き取り先の養母からいじめを受けながら、自殺未遂をしたり、望まない妊娠をしたりと過酷な人生を送る。やがて韓国に実母が生きていると知ったユスク(=スーザン)は韓国に戻って母との再会を果たす。
『ラブ』
1999年作品
監督=イ・チャンス 脚本=ソン・チナ 出演=チョン・ウソン、コ・ソヨン、パク・チョル
スランプに陥ったマラソンランナーミョンスは、国家代表選手としてアメリカにやってくるが、練習中に脱走し、遠い親戚のもとに身を寄せる。そこには幼いときにアメリカに養子に出された在米韓国人のジェニーがいた。恋にも人生にも不器用な男と女が少しづつ心を開き、前に向かって進み始める、さわやかなラブストーリー。