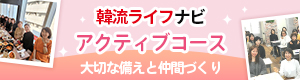取材レポ・コラム
映画関連
韓国映画をリードする女性たち
※2003年7月発刊「韓国はドラマチック」(東洋経済新報社)より。 記事の転載禁止です。
『JSA』『反則王』『アタック・ザ・ガス・ステーション!』『クワイエットファミリー』『ラスト・プレゼント』『新羅の月夜』(ビデオ題名『風林高』)……。日本で紹介されたこれらの韓国映画に共通していることは何か?
それは、女性がプロデューサーを務めた作品だということだ。韓国では1990年代に入ってから、女性の敏腕プロデューサーが数人登場し、右に挙げたように、次々と意欲作、ヒット作を生み出してきた。
それに加えて、ここ2年ほどは女性監督の存在が続くようになってきた。それも日本ではまだ数えるほどしかいない商業映画の分野にである。 韓国は儒教精神が根付いている国。日本以上に男性主義が強いという印象があったのに、特に『男の職場』という意識が強かった映画の製作現場に、いつの間にこのような女性パワーが炸裂するようになったのだろうか。
政治的・道徳的に正くない
素材で撮ってみたい
具体的にどんな女性監督たちが登場してきているのかを見てみると、1995年『ナヌムの家』でビョン・ヨンジュ監督(1966年生まれ)が現れる。ビョン監督は中央大学大学院映画学科出身。
『ナヌムの家』は従軍慰安婦を扱ったドキュメンタリーで、従軍慰安婦を初めて真正面から取り上げた作品として評価され、その後『ナヌムの家2』(1997年)、『息づかい』(1999年)とシリーズ3部作を発表し、2002年に『密愛』で商業映画デビューを飾った。
この作品は、『わが生涯、たった一日だけのとても特別な日』という小説を映画化したものだ。
2002年の東京国際映画祭の上映時にQ&Aに立ったビョン・ヨンジュ監督は、「従軍慰安婦を素材としたドキュメンタリーのときは、素材が政治的で誰もが正しいと考える問題だったために、誰もが支持者になってくれたことが逆に負担に感じられた。
だから、今度は政治的・道徳的に正しい素材でないもので撮ってみたいと考えました」と語った。
この言葉にあるように、『密愛』は、夫の不倫でうつ状態になった主婦が、自身の激情的な愛を経てひとりで生きていく姿を描いた、韓国では珍しい、女性のヒロインが物語を引っ張っていく作品だった。
1996年には、『三人友達』でイム・スンレ監督(1960年生まれ)が長編映画デビューした。イム監督は漢陽大学大学院演劇映画科出身で、フランスに留学して映画を学び帰国、助監督を経てのデビューだった。
その後2001年に『ワイキキブラザース』を発表。世の中の流れにうまく乗り損ねた売れないバンドマンたちの、しがなくて、切ない音楽劇で高く評価された。素材的にまったく女性色を感じさせないところは、デビュー作『三人友達』から貫かれている。
そして、最も若い女性監督として話題を呼んだのが、『ラブラブ』(1997年)のイ・ソグン監督(1975年生まれ)で、短編を経て、劇映画『301・302』のシナリオで評価され、ニューヨーク大学映画科在学中に監督デビューした。
2028年のソウルを背景に、漫画家と女性殺し屋の愛の物語が展開される作品で、興行的には失敗してしまったが実験的な作品だった。
地味なテーマを無名キャストで
撮って記録的な大ヒット
1998年には、『美術館の隣の動物園』のイ・ジョンヒャン監督(1964年生まれ)が登場。イ・ジョンヒャン監督は韓国映画アカデミー出身。青龍賞シナリオ公募大賞で自身のシナリオが大賞を受賞、自らメガホンを取ることになってデビューした。
内容は、ひょんなことから同居することになった男女のふれあいを描くロマンチック・ラブコメディー。シム・ウナ演じるヒロインが、大雑把でだらしないのに、生き生きとしてかわいく、今までになかったキャラの立った女性像で新鮮に映った。
2作目の『おばあちゃんの家』では、山奥に住む70代のおばあちゃんと都会からきた孫とのひと夏のふれあいという地味な題材を、無名のキャストで撮り、それが記録的な大ヒットとなって2002年の話題をさらった。
今世紀デビューの商業映画で活躍する女性監督もいる。
2001年にチョン・ジェウン監督(1969年生まれ)が『猫をお願い』を撮った。チョン・ジェウン監督は、韓国芸術総合学校映像院映画科出身。
短編を数多く撮った後、『少女たちの遺言』のスクリプターを努め、本編で長編デビュー。5人の20歳の女の子たちが、女性への偏見や保守的社会の中で、将来に向けて揺れ動く姿を繊細に淡々と浮かび上がらせ、数々の賞を受賞するなど高く評価された。
2002年には、イ・ミヨン監督(1963年生まれ)が、フランスでの映画演出の勉強後、『クワイエットファミリー』『反則王』のプロデューサーを経て、『バス停留場』で長編映画監督デビューを果たす。
世の中に適応できない30代の塾講師と援助交際の経験がある女子高生の愛の話だ。
同じく2002年に、『いい人いたら紹介してね』でモ・ジウン監督がデビュー。東国大学演劇映画科出身で、『友へチング』『海賊ディスコ王になる』などのストーリーボード(絵コンテ)作家として名を馳せ、韓国映画アカデミー在学中に長編映画の監督に抜擢された。
結婚紹介所の敏腕女性相談員が会員の男性に不器用な恋をする、ロマンチック・ラブコメディーだ。モ・ジウン監督については、「男性中心の韓国映画界で、現場経験がない20代中盤の新人女性監督が商業映画に挑戦することは破格的なことだ」と話題になった。
『嫉妬は私の力』のパク・チャノク監督はホン・サンス監督の『オー!スジョン』で助監督を務め、短編映画で注目されて長編デビューに至った。
昔の恋人を奪った妻帯者に、年上の新しい恋人まで奪われる危機に瀕した青年の嫉妬と羨望を繊細に描き出し、2002年の釜山国際映画祭で最優秀アジア作家賞をはじめ、ロッテルダム映画祭でタイガー賞を受賞、審査員団から「人間関係を考察する野心に満ちた映画で、強固な部分と繊細な部分が交わった演出と、俳優たちの演技の調和が引き立って見える」と高く評価された。
ほかにも、『唐辛子を干す』のチャン・ヒソン監督や、『空色の故郷』のキム・ソヨン監督など、山形国際ドキュメンタリー映画祭で上映された、インディペンデント、ドキュメンタリー作品を手がけた女性監督たちもいる。
制作サイドにまで広がる
女性映画人
2000年の段階で、韓国における女性の映画関係者の数は500人あまりになるという。メイクや衣装、また広報、マーケティングといった、以前から女性スタッフが多かった分野ばかりでなく、技術の分野、プロデューサー、監督といった制作サイドにまで広がっている。
そんな中、1999年の釜山映画祭の最中に行われた女性映画関係者の懇談会で、女性映画人の会の必要性が提起され、翌年の2000年4月に「女性映画人の会」創立総会が開かれた。女性たちのネットワークを作り、女性映画関係者の裾野を広げるための組織である。
ただの親睦団体にとどまらず、映画会社、撮影現場と連結した人材バンクを運営し、シナリオ、編集、撮影、プロデューサー、広報、マーケティングなど専門分野別にワークショップを行うなど、女性映画人たちの活動は目に見えて活発化してきている。
こうした、女性監督、ひいては女性映画関係者たちの最近の活躍ぶりについて、あいち国際女性映画祭のゲストとして来日した韓国映画のセールス会社イー・ピクチャー(e pictures)のチョ・ウンジョンさんに聞いた。
いい素材を持っている人に
チャンスは巡ってくる
――最近、女性監督たちが活躍していますよね。
「最近の韓国映画界は、若い映画監督たちに撮らせようという動きが出てきています。
長い間助監督の経験を経たり、映画学校を出たり、海外に留学に行って帰ってきた人たちが短編を撮ってそれが注目されて長編デビューに結びついたり、あとは韓国映画界ってシナリオも監督が書くことが多くて、常にいい素材はないかいつも探しています。
いい素材を持っている中には女性もいて、そういう人にチャンスが行くことがあるんです。特に女性だからというわけではなく、いい素材を持っている女性監督が多かったということがいえるでしょう」
――日本だと女性監督の作品ってインディペンデントで制作されるものが多いのですが、最近の韓国の女性監督の作品は商業映画が多いですよね。
「確かにそうですね。今の韓国では、芸術映画、低予算映画にはむしろ投資しません。50億ウォン(日本円で約5億円)クラスの大作には簡単に投資するんですが、5億ウォン(=5000万円)、10億ウォン(=1億円)くらいの作品には見返りも少ないと思ってか投資しないんです。
そんな中で女性監督はロマンス、ラブストーリーがうまいと思われていて、制作者もラブストーリーをやる女性監督とは一緒にやりたがる。受ける作品をやりたがるし、またやらせたがるんです。
イ・ジョンヒャン監督も本当は『おばあちゃんの家』のほうを先にやりたかったのですが、受けのよさそうなラブストーリーを先にやったのです。一度成功して初めて認められるのです。
女性映画を作ろうとそれに固執するというのもいいことかもしれないけれど、自分の声を入れるためにはまだまだ戦わないといけないんです。
『猫をお願い』のチョン・ジェウン監督も自分のメッセージをもっとたくさん入れたかったけれど、そうするにはたくさん戦わなくてはいけなかったし、いろいろ悩んだこともたくさんあったようです。
それでも少しずつ商業映画の中に自分の声を込める監督が増えてきているので、よくなってきていると思いますよ」
――女性ならではの難しさというのもあるんでしょうね。
「女性監督は往々にしてビジネストークがうまくありません。夜お酒を飲みに行ってそこでいろいろな映画の話をしたり、人脈ができたりするんですが、やはり女性映画人にとってはそれがつらいんです。
夜遅くまで男性と飲んで酒に酔うとセクハラのようになってくるじゃないですか。それを負担に思う人も中にはいるでしょう。
映画学校を出た人はまだ人脈があるだろうけど、そうじゃない人は難しいかもしれませんね。アイデアはたくさんあったとしても実現するにはね。
また『猫をお願い』のチョン・ジェウン監督は、シナリオを読んでみると5人の女の子の性格描写がすごく詳しく書いてあったんです。でもそれをそのまま撮ると長くなってしまう。巨匠だったら好きに作って下さいといわれるのでしょうが、彼女のような新人は涙を飲んでカットしなければならない部分が多々あったと思います。もうちょっとこうしたいというところがあっても、わかってもらうまでに倍以上説明しなくてはならなくて大変だったようですよ」
民主化運動の流れで
制作された映画に触発
――日本では商業映画を撮っている女性監督って本当に少ないんです。それも継続的に撮っている人はひとりかふたりでしょう。私は今まで日本と韓国における男性と女性の立場って似ていると思ってきましたが、ここに来てなんで韓国では女性の監督が大勢出てきたのかと思うのですが。
「1980年代の韓国の映画って、民主化運動の流れで、民主的、社会的なテーマのものが多くて、そういう作品が教育の場で使われることが多かったんです。
そういう社会的な映画を見ることによって触発された女性たちが、映画学科、映画サークルにどんどん入るようになって、そのサークルが自主映画を作るようになってきました。
最初は編集とか裏方の仕事をする女性が多かったんですが、サークルで実際に映画を撮っているのを見ると、やはり自分も参加したいとだんだん現場に出てくる女の人が増えてきたんです。
で、その人たちがまた触発されて自分が映画を撮ってみたいと思うようになって、短編を手がけたり、ドキュメンタリーを撮ったり留学したりしてだんだん女の人が育ってきました。そのサークルなどに参加していた女性たちが成長して今現場に出始めているんです。
それまでも商業映画を撮ってきた女性監督もひとり、2人はいたんです。イム・スンレ監督は、最初短編で認められて製作会社から『三人友達』のオファーをもらって長編デビューしました。でもこの後5年も撮る機会がなくて、やっと『ワイキキブラザース』を撮りました。
だから今出てきている女性監督たちも、デビューできても次がすぐ撮れるとは限らないと思います。でも今まで現場の影に隠れていて、活躍の場を模索していた女性たちが監督として育ってきている動きがあるのは事実です」
――だから1960年代生まれの女性監督が多かったんですね。女性が現場を取り仕切るということに周りの男性スタッフの意識に抵抗はないんですか?
「そういう不便さはないみたいです。というのも同じ学校を出た人や、一緒の釜の飯を食べた仲間同士という感じの人たちと組んでやることが多いので。
それよりも監督の低年齢化によって周りのスタッフのほうが年上ということがあるので、性差というより、年齢差で、新人監督の意思疎通のほうが大変のようです。そうした場合、男性監督の場合は一緒に夜通しお酒を飲んで話しができるけれど、女性の場合それがちょっと大変な人がいるので、不便かもしれない。
でもその分、女性はなんとかしなきゃと努力をするので、むしろ女性監督のほうが、気配りというか、意思疎通を図ろうという努力があるだけいいかもしれませんね。ちなみにイム・スンレ監督はお酒は強いですよ。
昔の女性監督は、というか男性も女性も、ドキュメンタリーの現場でさえ、お酒が飲めなきゃいけなくて、徹夜ができなきゃいけなくて、性的な冗談にも耐えなくてはいけないというようなのがあって、若い人って年上の人にやめてくださいとはいえなくて我慢しなきゃいけなかったんです」
――昔ってどれくらい前のことをいうんですか?
「1990年代半ばくらいまでですね。このくらいまでは徒弟システムで少しずつ上がっていく体制でしたから」
子供が産まれてしまうと
監督という仕事はやりにくい
――結婚生活と両立させている女性監督っていますか?
「1980年代の監督ですが、イ・ミレ監督はそうですよ。十数年前に、結婚して、子供を生んで、近じかまた新作を作るらしいです。
今の女性の新人監督はだいたい30代前半なので、結婚はこれからという人が多いのでは。中にはもう結婚している人もいますけど。韓国では結婚して仕事を続けていても、子供が生まれてしまうとやりにくいでしょうね。監督という仕事は特に。
日本より韓国のほうが難しいでしょう。というのも日本よりも福祉施設や託児所が少ないんです。本当は実家の母親や義理のお母さんに頼んだりするんでしょうが、それも大変なんです。まだ男性の中にも育児は女性がやるものだという考えをする人が多いので、お金がたくさんかかりますよ」
――みんなこれからそういう壁にぶつかっていくことになるんでしょうね。ところでチョ・ウンジョンさんはどういう経緯で映画界に?
「大学では映画科ではなかったんですが、大学を出てからやっぱり映画をやりたいと思って、1995年に映像院ができたので、入って勉強しました。
そこには高校を出たばかりという人や、社会経験を経てから入学した人とか、いろんなバックの人が入ってきたので、同級生といっても年齢差は12歳ぐらいあったかもしれませんね。『猫をお願い』のチョン・ジェウン監督ともそこで知り合いました。
私は映画理論科で、ここで映画の勉強をして釜山国際映画祭に参加し、映画振興委員会に入って海外業務部に行って、その後イーピクチャースに入りました。
映画に関心があっても、女性の場合、現場に出るのに体力的に無理なことがあるので、そういう場合は、マーケティングやPRに入ることが多いんです。入りやすいから。
でも制作をやりたいという人もいるので、そういう人はだいたいマーケティングから制作システムを学んでプロデューサーになっていく人が多いですよ。シム・ジェミョンやオ・ジョンワンといった女性プロデューサーはもともとマーケティングから入った人たちです」
――女性プロデューサーが多いということが女性監督を生み出しやすい土壌になっているともいえるんでしょうね。
「自分が大変な思いをしているだけに新人女性に機会を与えようと思う気持ちは強いでしょうね。
実際に『バス停留場』のイ・ミヨン監督は、ミョンフィルムで撮っているんですが、ここのシム・ジェミョンプロデューサーとは大学の同級生なんです。イ・ミヨンは『反則王』のプロデューサーでもあるんですよ。
そうやって友人関係で協力しあうこともあります。映画人の場合、それぞれのベクトルが同じほうを向いていると、プロデューサーやってた人が監督になったり、マーケティングやってた人がプロデューサーになったりとか、業種替えじゃないけど、臨機応変に役職が変わるということもありますね。
――女性監督の作品だということで、俳優たちはオファーを受けるとどんな反応になるんでしょうね。
「女優の場合は、女性が書いたシナリオの女性像には魅力を覚えてやってみたいと思う人が多いようですね。男優の場合はそれまでの作品を見て判断する人が多いですね」
男尊女卑の差別に苦しみながら
闘ってきた女性映画人たち
1980年代の民主化教育が今の女性監督進出の土台になっているというのは興味深い話だったが、なによりも映画界内の徒弟制度が薄れ、新人が出やすくなってきたという韓国映画界自体の変化が女性監督の進出を促しているといえる。
最近の映画制作は、スタッフ一人一人が能力に合わせて契約してチームを組むのが主流になってきているという。監督のカリスマ性や権威はそれほど意味をなさなくなってきてもいる。
そんな時代にあっては、性差ではなく、個人の能力が大きくものをいう。それに、1998年、イ・ジョンヒャン監督が『美術館の隣の動物園』で興行的にも成功したことで、女性監督に対する信頼感が高まってきたことも大きい。
ただ、今でこそやりやすい環境になっては来たようだが、やはりここに至るまでには男性社会でのさまざまな苦労や偏見に遭ってきている。
それをうかがい知ることができるのが、イム・スンレ監督のドキュメンタリー映画『Keeping the Vision Alive(原題:美しい生存―女性映画人が語る映画)』(製作総指揮:ジュ・ジンスク、企画:イ・スンジン)だ。
2001年の釜山国際映画祭や、2002年のあいち国際女性映画祭などで上映されたこの作品は、韓国の女性映画人たちへのインタビューを中心に構成され、男尊女卑の中にあって差別に苦しみながら戦ってきた女性映画人たちの声が語られている。
これを見ると、韓国社会がどれだけ女性に対して偏見や差別意識を持っていたがよくわかる。彼女たちが実際にどんなことをいわれ、扱いを受けてきたか、その中でどんなことを思っていたか、女性映画人たちの発言を映画の中から拾ってみよう。
まずはすべてのスタッフを現場で取り仕切る立場の監督から。
「授業で男性生徒に撮影を教えるときはカメラは目の高さ、でも女生徒だとカメラを床の上に置いたり高いところに置いたりします。きちんと教えてくれないんですよ」
──『ナヌムの家』など数々のドキュメンタリー映画を撮り、最近では商業映画『密愛』を撮ったビョン・ヨンジュ監督
「中学時代に映画監督になると決めた瞬間から男のようになると決心しました。もともと女らしくないけど、女らしさを出さないできました。男やプロデューサーたちに、か弱くて、もろいと見られたくなかったから、男のように振る舞うよう訓練したんです」
──『美術館の隣の動物園』『おばあちゃんの家』のイ・ジョンヒャン監督
次に、体力勝負といわれることの多い技術畑の女性スタッフたちの声。
「男たちは女の同僚を受け入れません。もし受け入れたとしてもそれは女を対等な仲間として認めるというより、職場環境をスムーズにするために受け入れるだけ。彼らは女性を信頼していません。女は遅かれ早かれ辞めると思っているんです」
──『魚と寝る女』の撮影助手クォン・ミヨン
「照明だけでなく、映画制作全般が女にとっては体力的に困難と考えられています。でも男にとっても厳しい職場であり、体力は関係ありません。難しいのはコミュニケーションです。チームワークだから難しいのです。本当にやりたければ挑戦します。できないとわかったら気がすむまでやってからあきらめます。まだ若いのですから」
──『JSA』の照明助手キム・ウンミ
「私は自分なら撮影監督になれると思っていました。心配はしていませんでした。他人からは難しいといわれたけど、努力すればなれると信じていました」
──『恋風恋歌』で韓国初の女性撮影監督となったキム・ユニ
そして、作品の総責任者である女性プロデューサーたちの考え。
「映画の仕事はうまく行かないことが多い。多くの試練が待ち構えています。私への批判や噂もそのうちのひとつです。気にしすぎて仕事にならなかったときもあります。だから’あばずれ’になることにしたの。最近では他人からいわれる前に”私はあばずれ“と宣言するようになりました。それが私の新戦略です。
女性には映画業界で自分の個性を伸ばしてもらいたい。女性たちは戦うことが多くて気の毒だと思う。そのせいで才能の表現が制限されますから。どんなに成功した女性プロデューサーでもマイナーな存在なんです。この社会では大部分の女性が根強い疎外感を感じていて、それをみんなが共有しているんです」
──『反則王』『スリー』などの制作に当たったオ・ジョンワンプロデューサー、映画社ポム代表
「この国で仕事の話し合いは酒を飲みながらします。どの飲み屋でもいいのではなく、行きつけの店だけです。私はそれが嫌でイライラします。
男は自信を持ちすぎで、女は自信がなさすぎる。何かするとき女は男より時間がかかるんです。能力の問題ではなく自信の問題です。女は自信がないから前進することができないんだと思います」
──『アタック・ザ・ガス・ステーション!』『ラスト・プレゼント』『風林高』などを制作したキム・ミヒプロデューサー、よい映画代表
「私が一緒に仕事をした女性たちは責任感が強く、仕事熱心だったけど、駆け引きしながら働くことがなかったです。目標を達成する作戦を練るより、よく働くのがとりえ。女に特徴的なことです。
新しいスピリットを持った映画はチャンスが大きいんです。『美術館の隣の動物園』が映画化できたのは、信念を持った女性プロデューサーのおかげです。今までほとんどの映画は男の視点で選ばれ、評価され、製作されてきました。もし違う物の見方を提示できれば、それは利点であり、チャンスとなります。女性にはそれができるのです。
フェミニスト教育を受けたにもかかわらず、家事と子育てをする責任を感じてしまいます。だから私にとって家庭はくつろげる場ではなく、職場と同じエネルギーを使うところなのです。でもそれが私を成長させたと思います。映画制作にも家庭にも世界にも責任を感じます。結婚と出産を経て、自己中心的ではいけないことを学びました。他人を気遣うようになったのです。
今必要なのはこの業界の女性たちが団結して環境を変えるために力を合わせることです」
──『JSA』などを制作したシム・ジェミョンプロデューサー、ミョンフィルム代表
という感じで、やはり映画作りは、制作費が大きいし、大量のスタッフを動かさなくてはならないため、他の仕事以上に女性に対する目が厳しかったことをうかがわせる内容だった。
本音の部分ではいまだにこうしたことが残っているかもしれないが、2003年はさらに女性監督に対する期待感が高まっている。
『猟奇的な彼女』の大成功で注目されていたチョン・ジヒョンが次回作に選んだのは女性監督イ・スヨンの『4人用の食卓』で、しかも人気の演技派スター、パク・シニャンも共演ということで話題を呼んでいる。
また、女性監督の作品というと、どうしても低予算系の映画に終始しがちだったが、キム・ウンスク監督の『氷雨』という作品は、予算が50億ウォンという、韓国映画の中でもビッグバジェットの大作映画だ。
しかもジャンルが韓国初の山を舞台にしたメロドラマで、カナダでのロケもあるという大がかりな作品に女性監督が抜擢された。キャストも、日本でも『美術館の隣の動物園』『アタック・ザ・ガス・ステーション!』などでおなじみのイ・ソンジェ、『秋の童話』のソン・スンホンに、キム・ハヌルといったトップスターが揃う。
女性も大作映画を任される時代がもうやって来ているのだ。これが成功すれば女性監督への偏見がまたひとつなくなり、門戸はさらに開かれていくことだろう。